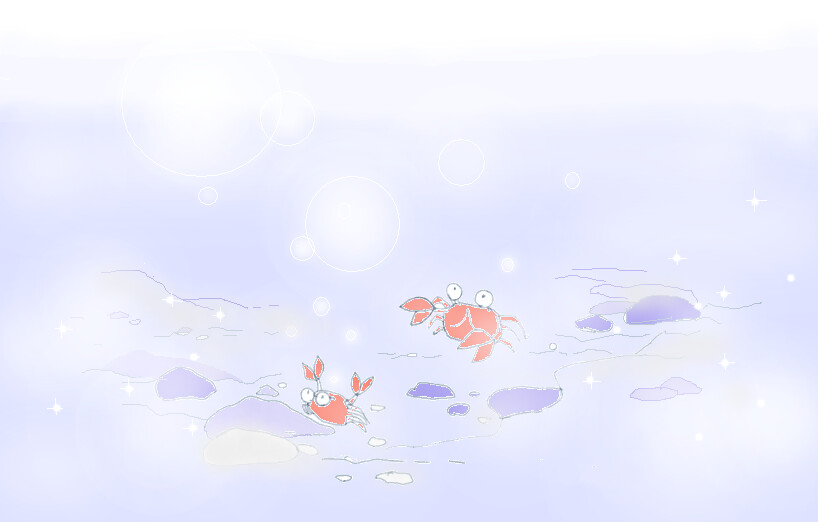
クラムボンはわらつたよ。
クラムボンはかぷかぷわらつたよ。
クラムボンは跳てわらつたよ。
クラムボンはかぷかぷわらつたよ。
宮沢賢治氏の童話「やまなし」。ほんとうに、美しい童話です。
静かな光が、ゆらめきとどく、透きとおる川の底。二匹の兄弟蟹が見つめる時の流れ。
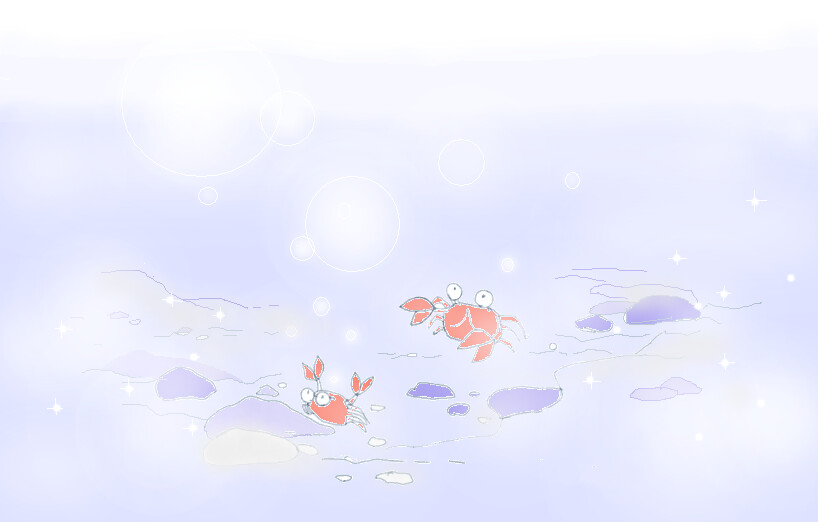
クラムボンはわらつたよ。
クラムボンはかぷかぷわらつたよ。
クラムボンは跳てわらつたよ。
クラムボンはかぷかぷわらつたよ。
宮沢賢治氏の童話「やまなし」。ほんとうに、美しい童話です。
静かな光が、ゆらめきとどく、透きとおる川の底。二匹の兄弟蟹が見つめる時の流れ。
この童話について、とくに、クラムボンとは何?と、解説や考察が、様々なされていますね。
アメンボや蛙と解釈されているものもありましたが、何となく、そうは思えなくて・・・。
美しい、ゆらめく川の水の光や流れに、子蟹たちが何を見るのか。何が見えるのか。
ここからは、賢治氏の心について、クツ様から頂いた言葉です。
さて、賢治氏の「やまなし」は綺麗なお話しですね。 これが発表されたのは、大正12年4月。 しかし、すでに10年には初稿が成立していたという説もあります。 大正10年は原敬首相が暗殺され、共産党員検挙が始められた年。 して、大正11年には、最愛の妹、とし氏が逝去しています。 何か、このあたりのことが、オーバーラップし、 「クラムボンは死んだよ〜殺されたよ〜死んでしまったよ」という表現になっており、 何よりも人を憎むことを嫌い、何にでも善を求めようとした氏が、 最後に「私の幻燈はこれでおしまいであります。」と結んだ所以は、 こんなところにあるような気がしてなりません。 クラムボンは蟹のクラムを捩ったという説が有力です。 他にも、諸説あるようですが、 氏は、物を書くのに、トラップを仕掛けたり、 第三者が深く読み込むことを推測し、その裏をかくようなことはしなかったから、 きっと、この物語に登場するのは、沢蟹だと思って(思い込んで)います。 氏も物語の中で「親子の蟹」と記していますので、 これを無理に講釈つけてまで、主人公を変える必要はないかと。。。 岩手の川で以前遊んだ時にも、渓流には沢蟹がたくさんいました。 幻想的な童話ながらも、ごく小さな渓流の中から、 過ぎ去る一年を通して、浮世絵のうつり変りか、人間の業を描いたものではと、 私は勝手に推測してしまいます。 ただ、「蟹=クラムボン」ではなく、これが何を表現したものなのか、 未だ私も理解できていません。 しいて言えば、仏様の光??? クツ様が、BBSに書き込んで下さったものを、 |